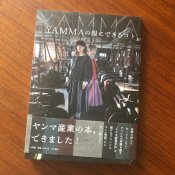CALICOとインドに出会った旅 2014初春
目次 1:CALICO(キヤリコ)について 2:ヤンマとキヤリコの出会い 3:インドの綿織布キヤリコについて 4:ガンジーとチャルカ(糸車)について

1:キヤリコについて
CALICO : the ART of INDIAN VILLAGE FABRICSは、
小林史恵と増住有希によるインドの手仕事布ブランドです。 しかし、その活動はただデザインをして、売ることだけでなく、 インド大陸各地(本当に広い国土に点在してます!)にある団体やデザイナーと連携してインドの手織物産業の持続的発展を支援する活動もしています。二人はまず、各々の仕事でインドに住むことになります。 小林さんは経営コンサルタントとして4年前に、増住さんは大手商社のバイヤーとして6年前に。 そこで、それぞれの仕事をしながら、インドの手織り布、手刺繍などの手仕事布に魅せられ、インドの農村のくらしに強い関心をもちます。 インドの布の素晴らしさだけでなく、手仕事の豊かさや農村の慎ましくも美しい暮らしに出会うのです。 そうはいっても、イイモノだからといって存続できる世の中ではないのは、インドも日本も一緒でした…
二人は自然に出会い、意気投合。 2012年からインドと日本を拠点に活動をスタートさせました。 この尊い豊かさを日本や世界と分かち合いたい、 インドの生産者と協力し、インドの農村に残るクラフトマンシップとその土地での社会的効果、事業継続性を大切に考えながら、村々で作られてきたカディ(手紡ぎ・手織り)布、カンタなどの刺繍布、手染め布、手織り布と向き合い始めます。
2:ヤンマとキヤリコの出会い
また、キヤリコは、自身の活動に共鳴し、関心をもつ人のインドでの手仕事布事業支援もしており、 そんなこんなで、ある人の紹介でこの1月に、 ヤンマ山崎、たまたま吉祥寺に来ていたCALICOの小林さんに会うことが出来たのです! ほんの1時間強のコンタクトです。 まあ、ヤンマ、その時点では失礼な話ですが、カディってあの手紡ぎ手織りの素朴な布ね〜 見てみたいな〜それにしても手紡ぎで布って嘘でしょ〜くらいの気分でした。 しかし、小林さんの持っていたカディを見せてもらった瞬間に 「全然違う…」と感じました。 私は何か誤解をしているのかもしれない… このギャップは、現地を見ないと埋まらない、と即座に判断。 「とりあえずインドに行きます!」と、山崎、言ってしまったのでありました。

さてさて、インドに行ったのはそれから3週間後。 我ながらフットワークが軽いです…しかし、今回は異常に軽いです^^ 珍道中が始まります… と言いたい所ですが、インド滞在の1週間の詳細はえげつないので割愛し(笑)、 結論として、私はインドで楽になりました! (えげつないくらい、楽しんでしまったという意味です^^;)
全くの誤解というか無知だったのですが、まず、インド人のイメージが全然違いました。 インド人の仕事は丁寧で、キャラクターはのんびりにこやかです。 すごく丁寧に説明してくれますし、小さな店でも従業員が多くて、 細かく気が利いて「ありがとう」を言う機会が多かった。 いわゆる、amazonが前行程機械化を計っている真逆の状況です。 信じられない砂埃にまみれながら、心が洗われました…
そして、じわじわと、なんか、この私の感じているインドを伝えたい!んだけど、 どうしたら伝わるんだろ〜そもそもこれは何なんだろ〜と思っているうちに、 ああ、だからCALICOが出来たんだな、と理解出来ました。 本当に、このインドの感じ、伝わるといいな〜キヤリコさん頑張って!と思い、 「一年間に度々日本とインドを行ったり来たりしていると、なかなかインド側に目が行き届かない」という小林さんの話を聞き、 「うち、日本での宣伝とかやるよ〜」と自然に言っていました。 相変わらず、非常に軽いです(笑)
小林さんも、増住さんも、とても魅力的で、ヤンマがしゃしゃり出るところでもないかもしれないのですが、とりあえず、私も何かしたい!と思ったのでした。
そして、肝心な、CALICOの製品ですが…これが素晴らしい! キヤリコを代表することになりそうな「エアリー」シリーズは、 柄もなく極めてシンプルですが、この一ヶ月、展示してみたり、撮影したり、もちろん使ってみたり、で、山崎ずーっと触れ合っていますが、 使えば使うほどふわふわ感にも味が出て魅力的になって行きます! 色もとても使いやすく、日本人の顔色にあう品の良いカラーリングです。 ジャムダニやアッサム刺繍、これからはカンタ刺繍も紹介出来るかもしれませんが、 インドの布の力を損なわないようなデザインがされ、 きっと洗練された手仕事を見せてくれることでしょう。
3:インドの綿織布「キヤリコ」について
calico(キヤリコ)は16世紀頃から広く世界に知られてきたインドの綿織布のことを言います。
風合いがよいだけでなく、薄くて丈夫で染めやすいキヤリコは、欧州や日本を含む極東で人気を博し、東インド会社の重要な交易品として重宝されました。 やがて自国産業の衰退を恐れたイギリスやフランスでは、インドキヤリコ輸入禁止令、使用禁止令が発令されましたが、それでもインドのキヤリコのような布を手に入れたいと考えた人々によって飛び杼や紡績機が発明され、産業革命を引き興すきっかけとなりました。 (おおお!ヤンマの裏テーマ!産業革命!^^) 世界の歴史をも変える力をもったパワフルなインドの手織り布。 日本とインドの布産業の交流も色々ありそうで、これからもっと調べたいと思います。
そう、私は、インドの布に「力」を感じたのです。 繊細な見た目とは真逆の訴求力。 その柔らかさの中に、ものすごく深く強いガンジーの思いを感じたのでありました。
現在世界の手織布の95%以上がインドで生産されており、約430万人の織人さんがそれを支えているといわれますが、近代産業の発展とその賃金差の拡大によって、次代の担い手を失いつつあります。 日本や中国の伝統織物の世界に起きたことと同じことが、この手織物大国のインドでも起きようとしています。
これを止められるのは、インド人だけではないと思います。 一度失ったものはそう簡単に再び立ち現れることはない… それを知っている日本人だから出来ることもあると感じました。
4:ガンジーとチャルカ(糸車)について
インドの布が凄い、と書いてきましたが、
インド人にとって、糸を紡いで、織ることは、全く意外な意味を持っていました。 アシュラム(ガンジー主義の道場)では、朝晩のお祈りの時間には必ず皆がチャルカ(糸車)を持って集まり、糸を紡ぐ。 カディとはただの布ではなく「思想」なのです。インド独立の父ガンジーは、イギリスの支配のもとインド人の奴隷化、貧困が進む原因を「イギリスの生んだ近代機械文明をよいものだとして受け入れたインド人自身にある」と言っていました。 近代機械文明のもたらした物質的豊かさを幸福として疑わない時代に、ガンジーは機械文明が人類を破滅に導くことを必死になって説いた。 そして、そうした道ではない真の文明を創り出す経済的・思想的基盤として、チャルカ=手紡ぎ車を掲げました。 「農業を百姓の胴体だとすれば、チャルカはその手足です。インドの人口の八○パーセントを占める百姓が歩む道は、この二つを守ることにしかないのです。インドを非暴力的手段で守る唯一の武器はこのチャルカしかないし、インドの本当の独立はこのチャルカから紡ぎ出されるカディーなしには考えられません」
ここで私は、突然出会った「カディ」に導かれて、 あっという間にインドに辿り着いた意味を知りました。
カディは見れば見るほど「信じられない」布です。 この細い糸が人の手で紡がれ、できた細い糸をまた人が織る。 カディを触りながら考えるのです、ガンジーの言いたかったこと。 機械化を完全に導入し、経済大国になった日本が失ったもの、 自然、伝統、文化、人間的な豊かさ… ガンジーの伝えたかったことが今の今になってよく分かるのは、 とても皮肉なことだが、いつでも、今日がベストだ! なんでも、今日から始めれば良いんだ!と思って、日本に帰ってきたヤンマでした。
CALICOの布を手に取って、その優しさと力強さを感じて欲しい、と、願っています。